5歳児に試してみた。とても興味深い結果となった。
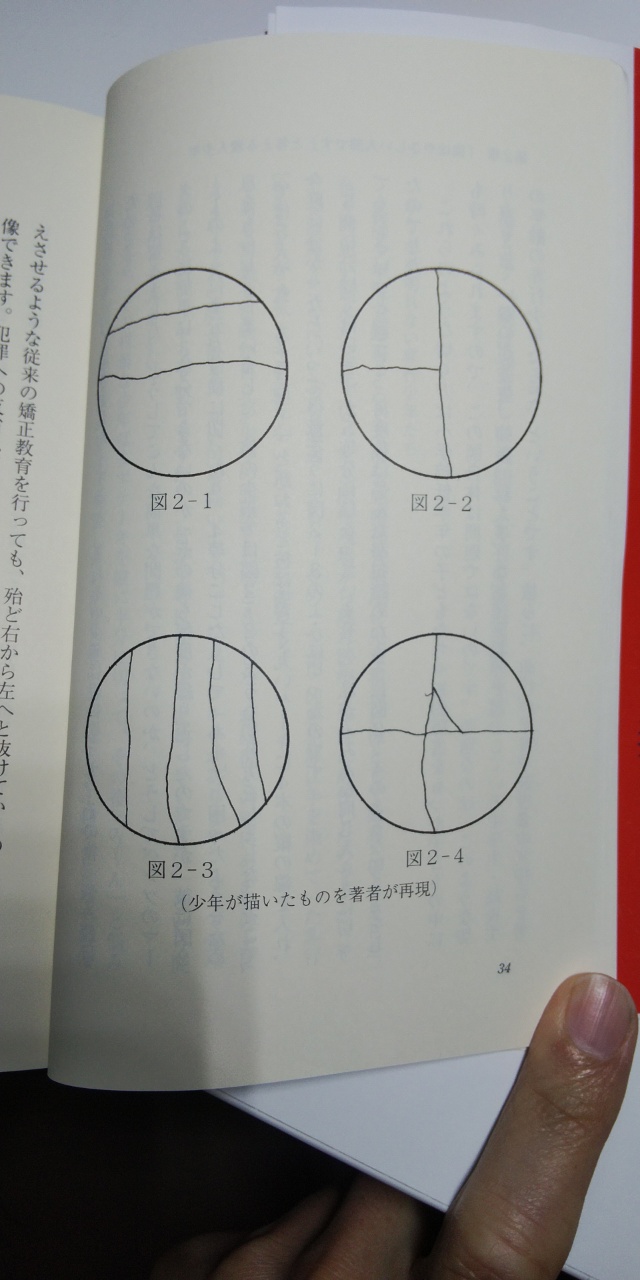
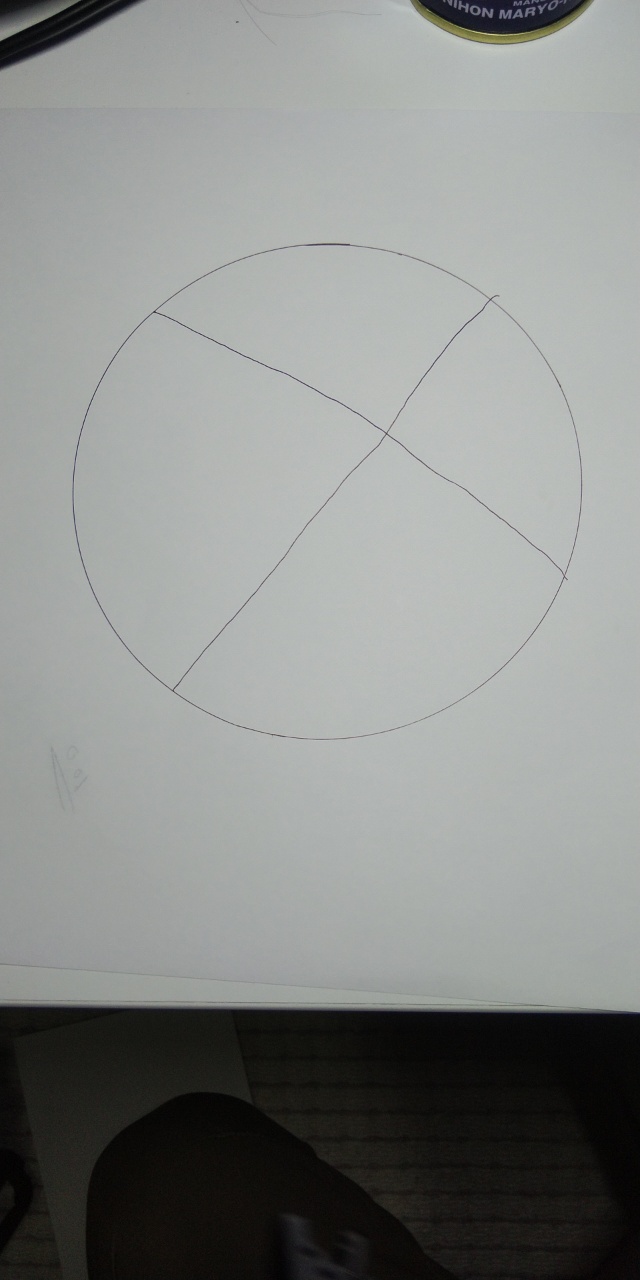
左が非行少年たちが書いたケーキ三等分の図。右は5歳女児の書いた図。
女児には「パパとママとあなたでケーキを3つに分けて。同じ大きさだよ。自分だけ多くしたらダメだよ」と言って書かせた。
結果、4等分となってしまったが、余った1つは友達にあげるのだそうだ。
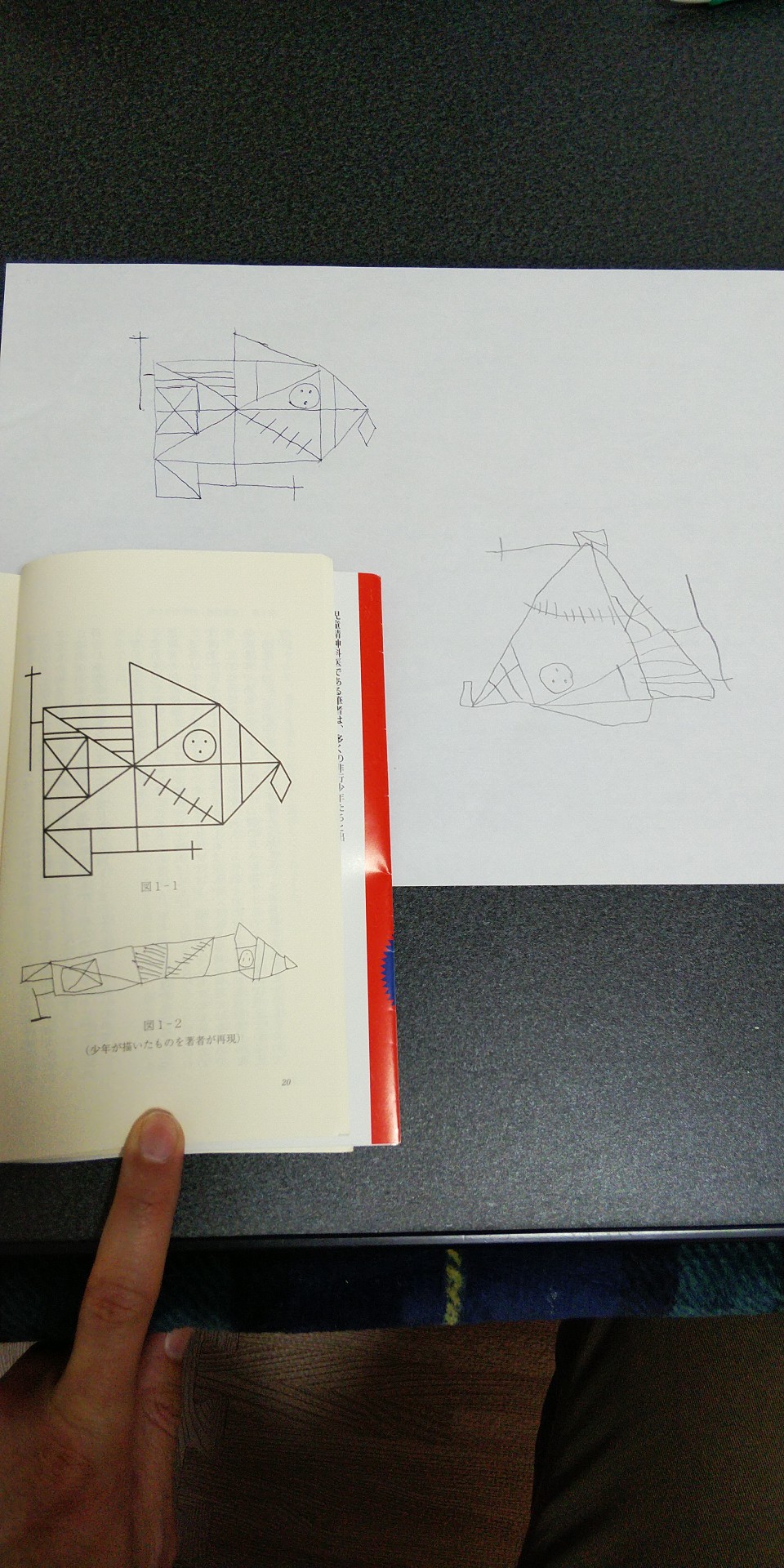
上は自分が書いた絵、右は5歳女児の書いた図。
本の下部は不良少年が書いた絵。
考察
実験結果から、非行少年の図を写す能力は、5歳と同じくらいのように見える。似ている。
この書き写しがある程度できるようになる過程は、自然に覚えるか、自然に覚えるよう誘導するか、教えるか、が考えられると思う。
5歳の場合、紙に絵をかくことが割と好きだし、外で遊ぶことも自由に行っている。割と活発な子だ。
非行少年は、非行を行うまでの15年間ぐらいで、これくらいの能力しか育たなかったという事になる。
それは育つ場面が無かったし、与えられなかった、教えられもしなかったのだと推測する。
どうして、そうなったか。責任は全部親だと思う。
これを書き写すためには、見る力が必要なのだとこの本の筆者は言う。
見たものを正確に認識する能力だという。
これは、紙に線を書く能力に限ったことを言っているのではなく、物事を正確に認識する力という意味なのだ。
だから、これができないということは、いろいろ世の中のことを、歪ませて間違って認識することになると。
簡単に言えば、そういう間違った認識が非行に結びつくようなのだ。
非行は、物事を間違って捉えて、それにより怒り、非行におよぶ。
あとがき
少年院に入った子たちは、まずドリルをやらされるのだという。不足している能力を鍛えるためのドリルだ。
鍛えれば成長していくようなのだ。不足している能力を成長させて、少年院から出るのが目標。
ということはこうなった理由の原因である能力不足は、
能力不足となった理由は、教えていなかった、教える場面が無かった、そういう事に間違いないと思う。
そして、いろいろな能力が足りないまま成長していき、小学校高学年くらいから悪いことをしだしていく。
経験上、悪いことをする子供の親は、そういう親であることが多い。
2020.4.27
非行少年は感情を抑えるのが苦手で、特に怒りを抑えるのが苦手なのだそうだ。感情のコントロールが上手でないということ。
また、想像力が足りないゆえに、怒りがすぐに湧いてきてしまう。
怒りによって引き起こされる二次災害はたくさんある。
「犯罪を犯して施設に送り込まれた子の半数が、虐待を受けている」
こんなことが本に書かれていた。
とても興味深いし、重要なことだな。半分もいるのか、ということ。
必要なしつけや、教育をされなかった場合、
上の図が上手に写せなかったり、怒りを抑えるのが苦手になるのだと推測できる。
虐待をしていた家庭で、その教育やしつけが、できていると思えない。
ここで自分が見た乳児2人を見て感じたことがある。
乳児はいつでも泣いている。理由もわからず泣く。泣き声というものは、怒りが湧いてくるのだ。
怒りが湧いてくる、という生理的現象?は否定できない。というのは、逆に一生うるさい状態で平常心が一生続く人間がいるのか?と。
でも、自分は怒りが湧いてきても乳児を虐待はしなかった。
しかし、感情を抑えるのが苦手な人間が、親になり、子を育てることになったらどうなるか。
最近思っている。この感情は一歩間違えれば虐待につながる可能性は十分にあるな、と。
2020.4.27